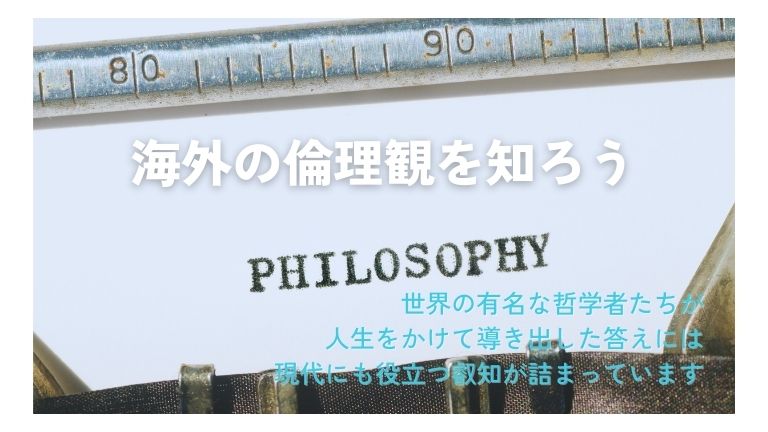今回は海外の思想にも触れてみましょう。
海外の倫理観、世界の哲学者がどのように考えたかを見ていきたいと思います。
ソクラテスの真理と徳
哲学の祖と呼ばれるソクラテスは、主に真理について追求した人物です。
ソクラテスは賢人たちを片っ端から論破して行きました。
それによって権力者たちの怒りを買い「国家の神々を信ぜず、若者たちを堕落させた」という根拠のない裁判で刑死します。
ここでソクラテスは「不正に対して不正で報いることは許されない」としました。
ソクラテスは全てのものにはアレテーがあるとし、人間におけるアレテーが魂を良いものにすることであると考えました。※アレテー=魂の優秀性や徳のこと
ソクラテスの教えとして有名なものが「よく生きる」ということで、よく生きるということは魂を良いものにすることであると考えました。
ソクラテスは相対主義を否定し、相対的には多様性が認められると言う良さがありつつも、物事の判断が難しくなると言う弱さがあるとしました。
ソクラテスには「無知の知」と呼ばれる逸話があります。
これはソクラテスが大切にしていた「汝自身を知れ」と近い言葉です。
「無知の知」とはソクラテスがソフィストと呼ばれる詭弁家の、相手を言いくるめる技術ばかりを追求する姿勢に対して、ソクラテスは「私は自分が無知なことを知っている」と諭した逸話です。※ソフィスト=職業的教育者
つまりソクラテスを無知であることを自覚した上で、何が善であるかを認識することができれば、自ずと善は実践されるとしています 。
ソクラテスは実践されない善は、善について知っているとは言えないとしました。
ソクラテスは真理が客観的で絶対的なものであると信じ、真理とはそれを実践できるということを含まなければ実際にはわかっていないとしています。
これは陽明学における知行合一と通ずるものがあります。
また、ソクラテスは徳についても考えました。
ソクラテスは徳に対して「徳は教えられるのか」「徳を生み出すことのできる単一の最高徳が存在するか」の二点に注目し、徳は教える事ができるものであり、正しい理性をもつことによって、人は徳を有する事ができると考えました。
プラトンの存在
・存在とは何か
ものの存在を表す概念に形而上と形而下という分け方があります。
我々が五感で感じ取れる形あるものを形而下といい、形而上は形を超越した目に見えない耳に聞こえない精神的なものを指します。
私たちは非物体的な存在を認めているが多くの宗教においては科学との対象となるものは本当の意味では存在しないとされています。
・目に見えない抽象概念の存在も信じるプラトン主義
私たちは非物体的な存在を認めているが多くの宗教においては科学との対象となるものは本当の意味では存在しないとされています。
プラトンはよく物事をイデアにたとえますが、イデアとは時空を超えた事物の本質のことです。
イデア論の例としては三角形を描く時の線に太さが生じていることを例として挙げる事が多いです。
三角形は三つの点とそれらを結ぶ線からなる多角形であって線に太さがあってはダメで、この状態は真の意味での三角形の条件を満たしていません。
つまり三角形のイデアは現実世界には決して存在しないとなります。
このプラトンの存在論が永遠の存在である神を信仰するキリスト教の考えと共に、ヨーロッパ人の発想の根幹をなしています。
アリストテレスの存在論と倫理学
アリストテレスはプラトンの弟子です。
アリストテレスは論理学・倫理学・生物学・天文学などあらゆる学問を基礎付けたことから「万学の祖」と呼ばれています。
アリストテレスは存在論を事物の本質は個物に内在しているとし、イデア論を形而上学において否定しています。
批判の内容として「事物の生成・消滅をうまく説明できない」(実体として捉えるべき)と指摘しています。
アリストテレスは私達が見たり触ったりしている個々の存在の本質は、その個々の中に存在していると考えました。
アリストテレスは事物の本質をエイドス( 形相) と呼び、事物が成立するにはエイドスに加えて素材・材料を意味するヒュレー (質料)が必要であって、 事物は全てエイドスとヒュレーの統一体であるとしました。
アリストテレスは倫理学について、幼少期から徳を身に着ける教育をすることで、徳を有する人間になれると考えました。
さらに徳について知的能力ではなくフロネシス(実践知=良識)こそが徳であるとしました。
・倫理学の語源
倫理学はラテン語で「エティカ」と言います。
「エティカ」はギリシア語の「タ・エーティカ」に由来し、倫理学的な諸問題という意味を含んでいます。この「タ・エーティカ」という言葉を造ったのがアリストテレスです。
「タ・エーティカ」は「エートス」(人柄)という言葉に由来します。
そしてアリストテレスはソクラテスの「よく生きる」 という言葉(ロゴス)を解明させるために 「エティカ」(倫理学)という名のついた本を書きました。
・エートス
アリストテレスは「エートス」について「魂のうちの、非理性的な部分ではあるが、指令を下す理性に即して、その理性に従うことができる部分の、性質である」と説明しています。
つまり人間の魂の「非理性的な部分」を「理性」と「理性的でない」部分に分けて考え、この「理性的でない」部分を「欲望」と考えます。
そしてその「欲望」の中でも、「理性」に「従わせることができる」部分を「エートス」(人柄であり、従わせる力)であるとしています。
さらに「エートス」は事物の「アルケー」(原理)を把握する部分とし、その自省する活動を「テオーリア」(観想)としました。
※この考察では非理性的な部分の中でも欲望的な部分に注目しています。
またアリストテレスは、人間は「理性と非理性に跨っている不安定な状態である」としています。
・アレテー
アレテーはギリシャ語で「徳」と訳しますが、人間の行動に対しての優れた面を指す言葉として使われます。
そしてアリストテレスは「人間のアレテー(徳)は肉体のアレテーではなく、魂のアレテーである」として、人間は魂が優れている者こそが、ソクラテスの「よく生きる」を体現していると考えました。
これは人間の心を「本来は善である」と考えた、孟子の「性善説」と通ずるところがあります。
アリストテレスは「アレテー」を「エトス」(習慣)から生まれるとし、習慣化されたことで徳を身に着けたことになると考えました。
「エートス」と「アレテー」この二つの言葉を解釈すると、倫理学は「人間が「エートス」を用いて自省し、「アレテー」に従って「よく生きる」を実践するための学問」と言えます。
これをアリストテレスは「人柄に関わることどもを考察する学問」としました。
デカルトの物心二元論
物心二元論は近代哲学の基本的枠組みとして知られています。
デカルトは理性による合理的推論を重んじる「大陸合理論の祖」となりました。
デカルトが目指したのは学問を確実な土台の上に基礎づけることです。
デカルトの方法序説に良識はこの世で最も公平に分配されているものであるとして始まりますが、良識とは理性のことをいい、人間が理性的な存在であるということは全員が分かっている事として、理性を正しく用いさえすれば誰であっても正しい推論が可能であるとしました 。
これを哲学の第一原理と言います。
哲学の第一原理を見つける方法には、「方法的懐疑」という手法を用いて、絶対確実な原理を発見するために、少しでも疑う余地の残るものは退けてしまうという知的手続きを行います。
絶対確実なものには、感覚、常識、数学なども当てはまらず、唯一「自分自身が現に疑っているという事実」こそが疑いのない絶対確実な原理としています。
私は思考することでここに存在し、生きている。実在しているという意味です。
つまり神が私を作ったのではなく、自分が思考し、思考すること自体が自分の存在を証明している。考える自分がここに存在することで物質の自明性の他に、霊魂の実在を証明したことになります。
これがデカルトの「考える故に我あり」で、考える自我がここに存在するということです。
このことからデカルトは肉体と魂が完全に区別し、物質的な世界を物理的な因果法則だけで説明することが可能になりました。
物心二元論の問題として精神と身体の相互交渉をうまく説明できないということが挙げられます。
行動主義を含めて心的過程を、全て物理的過程として説明できるという哲学的立場を、物理主義または唯物論と言います。
心理現象を何の機能として説明しようとするのが機能主義です。
心の哲学としてトマス・ネーゲルはクオリア(感覚質)と呼ばれる概念を提唱しました。
クオリアとは人によって感じ方が違うという独自のクオリアが存在することといえます。
※パスカルの人間は考える葦であるはデカルトの考える人間(コギト)を 大前提にして言われた言葉です 。スピノザもデカルトの子分です「デカルトの哲学原理」を書いている。
ハイデガーとサルトルの存在論
ハイデガーやサルトル達は実存主義を唱えた人物で、実存主義の実存とは「現実存在を縮めた表現であるものの現実(実存)のあり方」を意味しています。「今ここにあるひとりの人間の現実存在(=実存)としての自分のあり方」とも言います。
この概念は西洋哲学で極めて重視されてきた本質概念と対比されます。
本質とはあるものの核心的な性質のことで、これに対して実存とはあるものの現実のあり方を指し、そこには非本質的で偶然的な性質も全て含まれることになります。
つまり、「いかなるものであっても、それを実存において捉えるならば、それは世界で唯一無二の存在である」ということです。
ハイデガーは存在することと存在するものをはっきり区別しなければならないとし、本当に存在するものは何かということではなく、何かが存在するとはいかなることなのかということを探求しました。
そしてハイデガーは、ソクラテス以来の西洋哲学がこの根源的問いを忘却してきた(存在忘却)として、存在論の歴史を解体し西洋哲学を根本的に転換しようと構想しました。
ハイデガーは議論の手がかりとして「事物的存在」と「現存在」に分類しました。※事物的存在は物、現存在は人間のこと
この分類は、事物的存在をただそこに存在するだけとし、現存在を人間が生きているということを明確にする為の定義であると言えます。
例えば YouTube などを 受動的に見るような現実逃避するような姿勢の人間は、もはや固有の存在(実存)ではなく単なる人の群れの一員に成り下がっているといいます。
このような人間をハイデガーはダス・マン(世人)と呼び、これは「大量生産された規格品に過ぎないような人間の没落した姿だ」という意味です。
そして自己の根源的な固有性に目覚めるには知恵の存在を自覚することが重要であるとしています。
これに対してサルトルはその人が何者であるのかその人の本質というものはその人が自分の人生のプロセスの中で少しずつ選択し決断し創造していくものとし、人は自由であるということの責任を背負いつつ能動的に生きるべきだと訴えました。
フランシス・ベーコンの経験論
因果関係という概念を否定する人物にイギリス経験論の祖フランシス・ベーコンが挙げられます。
イギリス経験論はあらゆる人間の知識は経験に由来すると考えます。
ベーコンの経験論を一層推し進めた哲学者が、社会契約論者のジョンロックで、一切の生得観念を否定することで経験論を徹底させました。
しかし経験論には難点があり、それは経験論が注視する帰納法の抱える根本的な問題です。
帰納法とは個別的な知識から普遍的な法則を導こうとする方法で、帰納法的推論はすべて論理的に誤っています。
つまり帰納法は可能性の高い結論を出せても確実な結論は出さないと言えます。
よって経験則と呼ばれるものは、全て帰納法に導かれたものであるため、蓋然的な性格を持っており、本当の意味での法則とは言えません。
ヒュームの懐疑論
ヒュームは帰納法の批判として、帰納法が成立するためには自然の斉一性が成立しなければならないとしました。
自然の斉一性とは、「自然界は常にどこでもいいような法則にしたがっている」という仮定であって、自然科学が成立するための根本条件と言えます。
自然の斉一性を証明するためには帰納法を用いざるを得ず、循環論法に陥ってしまいます。
自然の斉一性が成り立つ理由として、これまでずっとそうだったからという事実があげられますが、これまでそうであったことが、これからもそうであることは保証しないと言えます。
ヒュームはさらに因果性を否定しています。
ヒュームによると原因と結果の関係は観察される事実ではなく、それらの出来事に繰り返し触れた結果、習慣として心に生じる観念に過ぎないとしています。
しかしヒュームは因果性が存在しないとは言わずに、因果性は心の習慣であり、人の心の中に存在するものとしています。
カントの道徳論
カントは主に道徳的義務論について研究しました。
カントは、「行為の道徳性」を行為のもたらす結果によってではなく、その動機によって測られるとしました。
つまり道徳な行為であることを自分の内なる声に基づいて自律的に行われるものでなければならず、義務であるが故にそれを行うとしました。
カントが説く道徳的行為を導く意思(善意思)は、 道徳の世界で成り立つ普遍的な法則(道徳法則)に従おうとする意思のことを指します。
カントは道徳法則を次のように定式化しました。
「君の意志の格率(私的ルール)が、いつでも同時に普遍的立法の原理として妥当するように行為せよ」(定言命法)
つまり、いついかなる時も普遍的法則にしたがって真実を語れと言っています。
しかしカントの説は感情をあきらかに無視しているので厳しく批判されています。
ベンサムの功利主義と道徳
功利主義とは行為の結果によって規範を使い分けるべきだと考える「 善悪(正義)の基準を有用性(功利・効用)に求める」、つまり役に立つ者こそが望ましいといった主張です。
また功利主義においての道徳は、功利(幸福と利益)の最大化を達成することです。
そしてベンサムは善とは快楽を増す行為のことであるとしました。
これは個人的な善のことを述べており、社会全体における善をベンサムは、社会というものはフィクションに過ぎないとしています。
これが最大多数の最大幸福という合理主義のスローガンです。
しかし功利主義には快楽・幸福を客観的に測ることができない等の問題点がありました。
この問題をベンサムの後継者であるJS・ミルが質的功利主義を提唱し、ミルは功利主義論の中で「満足した豚であるより、不満足な人間であるほうがよく、満足したバカであるより、不満足なソクラテスであるほうが良い」という言葉を残しましたが、批判は残ります。
①個人を重視するあまり、全ての人格を一まとめにしている(多数を重視せよ)
②欲求を実現する時の質(プロセス)が問われていない(結果だけを重視)
③幸福の分配についてがあいまい(コストだけを重視するのか?)
この功利主義に変わって台頭してきたのがロールズによる正義論(公正としての正義)ですが、資本主義の体制を危険に晒すとして主張を曲げざるを得ませんでした。
結果としてカントとベンサムの理論を使い分けることで腹落ちさせることになりそうです。
チャールズ・サンダース・パースのプラグマティズム
正しさとは何でしょうか?
哲学とは真理を探究し物事を理論的に把握する事と言えますが、これに異論をぶつけたのが、19世紀にアメリカで生まれたプラグマティズムです。
プラグマティズムは実用主義とも言われ金儲けに役立つなどの実用ばかりを追求するアメリカ的な思想として蔑まれてきました
しかし近年ではプラグマティズムの再評価が高まっています
プラグマティズムとは知識や理論の正しさを行為によって証明します。
プラグマティズムの提唱者とされるチャールズ・サンダース・パースは「ある対象の概念を明晰にとらえようとするならば、その対象がどんな効果を、しかも行動と関係があるかもしれないと考えられるような効果を及ぼすと考えられるかということを考察してみよ。そうすればこうした効果についての概念はその対象についての概念と一致する」としています。
これをプラグマティズムの格率と呼びます。
このプラグマティズムを世に広めたのがウィリアム・ジェームズです。
自由
自分の行為を自ら決定する、この意思のことを哲学用語で自由意志と言います。
エラスムスは人間が自由意志を持っていると論じ、ルターやスピノザらは自由意志は根拠がないと論じ、カントは人間だけが必然性を越えられる独自の存在だと論じました。
確かに自由意志論には難点がありますが、自分が住んでいる国よって考え方が変わりそうです。
ヘーゲルの市民社会論
カントによると「自由は理性的に自分を統御し、自分がなすべきことを毅然と行うときに成立する」としていますが、カントを心酔しているヘーゲルは、自由について、「単に個人の心の内面で成立しているものではなく、共同体において具現化されるべきもの」としています。
これはアリストテレスが人間はポリス的(社会的)動物であることから 、前提として人は本来、他者とともに生きることを望む存在ということからも考えられます。これは承認欲求からも考えられます。
さらにヘーゲルの特徴として市民社会と政治社会(国家)を分けて論じた点です。
・ヘーゲルの市民社会
①全ての人々の労働と欲求の満足によって、個々人を満足させる
②この満足させる行為を、司法活動によって保護すること
③①②の偶然性に配慮し、福祉行政と職業団体によって、特殊利益を1つの共同体的なものとして管理する事
このような個々の利益を追求する社会、共同体としての市民社会(資本主義社会)の事を「人倫の喪失」とし、人倫の回復を国家に求めました。
ヘーゲルの法の哲学は正しさについて根源的な考察を加えたもので、ヘーゲルは真の正しさを人倫とし、重要な点は人倫を道徳としてしっかりと意味付けたことです。
つまり人倫とは良さを現実化するための客観的な社会制度であり、その実現においては、人間を内面から規律する道徳と、 人間を外面から規律する法の力が必要であるとしています。
民主主義と社会契約論
まずはホッブスが「リヴァイアサン」で「人間は利己的な存在であるから、放っておくと自分の利益を追求するあまり、争いが起こってしまう。これを治めるためにはリヴァイアサンのような巨大な権力を持った存在(国家)が必要だ」と唱えました。
ホッブスの思想は、政府なしでは孤独・貧困・悲惨・暴力的・短命な世界になるという無政府状態に関するほとんど万人の発想をカタチづくってしまいました。
無政府状態な世界を自然状態と呼び、自然状態では「絶え間ない紛争と喧嘩があり万人の万人に対する戦争となる」としました。
次にロックが「統治二論」で「人間は放っておいても平和な社会は作れるが、平和と安全をより確実なものにするために国家が必要」と考え、「国家のモノを利用する時は統治の権威を受け入れる」という暗黙の同意という概念を導入しました。
そしてフランスの思想家であるジャン=ジャック・ルソーの社会契約論はフランス革命の理論的支柱になりました。
社会契約論とは国家の起源を人民の契約に由来するものとみなす学説で、ルソーは民主国家で採用されている間接民主制を正面から批判しています。
なぜなら間接民主制は本質的に特殊利益のぶつかり合いを生むシステムだからです。
特殊利益は個人や集団の私的な利益のことを言います。
農家の利益・高齢者の利益・企業の利益・地域の利益・特殊利益のぶつかり合いが起こると、結果として社会全体の利益が損なわれることになります。
つまり各業界の代表は限られたパイの取り合いに陥り、社会全体にとっての利益というものを考えていないと言えます。
これを改善する方法として国民全員が特殊利益を棚上げし、公共の利益を目指すようにすれば良いとしました。
つまるところ譲り合いの精神が重要であると言えます。
ルソーは個人や集団の私的な意見を「特殊意思」と呼びその社会的総和を「全体意思」と呼びました。
例えば国政選挙や世論調査などは全体意思と言えますが、全体意思は社会にとって好ましくない結果をもたらしてしまうことがあります。
そこでルソーはみんなにとって望ましい答えをみんなで決め、そのみんなの総意を「一般意志」と呼びました。
一般意志ではヴォランテ・ジェネラールというものがあって、みんなが当然もつ考えとして、自らの意志で税金を払うことと、兵隊になることが、 社会契約(コントラ・ソシアール)だと主張しました。
しかしこの一般意思は、現代では否定されます。
なぜなら国民の総意を分割することはできないし、国家の規模感で全人民の総意も実現が可能とは思えないからです。例えば、投票率の低迷は多くの先進国に共通する問題で、残念ながら日本も例外に漏れることなく当てはまっています。
ルソーが国民皆兵制度の徴兵令を憲法体制に入れることを発案し、誰も払いたくない税金を無理やり国がとっていいという思想を作ったとも言える 。ルソーの国家観ではエリート官僚が統治するのが理想ということになりますが、これでは国家の暴走は抑えられません 。
※ルソーはフランス革命の人権思想と、人類の絶対平等思想「人間不平等起源論」と超過激な人民主権論の生みの親です。フランス革命はロシア革命と中国革命にも繋がりました 。
同時期に活躍したモンテスキューは、「法の精神」でロックの権利の分立を発展させ、権力の暴走を止めるための権力分立を提唱しました。
権力分立とはあらゆる権力は腐敗すると言う経験則に基づく仕組みです。
結論として民主主義は政府(ガバメント)と統治(ガバナンス)にまとめることができますが、政府は必ず武力を元にしているのに対し、統治は必ずしもそうとは限らないということです。
ミシェルフーコーの権力
真理とは何でしょうか?
権力とは相手に望まない行為を強いる力と言われます。
ミシェルフーコーはマイノリティの権力と戦いました。
フーコーによれば、自律的に内なる声に従って生きているとされるカント的な主体とは、既成の規範を内面化させる、従順な囚人のような存在にすぎないと言います。
そして真理とは、人々が正しいものと認める規範の体系に他ならず、そうした心理を人々が無批判に受け入れ再生産するところに生の権力が成立します。
つまり真理=権力と考えられます。
古典的な死の権力とは違い近代以降の生の権力にあっては支配は人々の意識のレベルにまで浸透しますが、人々がそれを権力と感じないようになるほどに内面化された不可視の権力が、今日の権力に他なりません。
まとめ
倫理学こそが人間生活の上で、最も重要な学問ではないでしょうか。
「何をすればいいのかわからない」「生きる意味を見出せない」若者が増え続ける日本にこそ、倫理学は必要だと感じます。
倫理学は現実世界に落とし込んでこそ意味があります。
この行動こそが、自分の生きる意味であり、やりたい事であり、目標になるのではないかと思います。